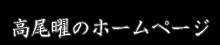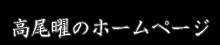豊川 楊溪(とよかわ ようけい)初代 ?〜1842
豊川 楊溪(とよかわ ようけい)初代 ?〜1842
福禄壽鶴蒔絵印籠
(ふくろくじゅにつるまきえいんろう)

 豊川楊溪(初代)作 豊川楊溪(初代)作
狩野養信下絵
 法量 : 法量 :
縦94mm×横47mm×厚26mm
 製作年代 : 製作年代 :
江戸後期 文化7年(1810)
〜11年(1814)頃
 鑑賞 : 鑑賞 :
徳川将軍家の奥絵師筆頭・狩野養信(1796-1846)の下絵によって初代・豊川楊溪(?〜1842)が作った印籠であり、徳川将軍家の所用品と考えられます。
豊川家に残された「印籠下画帳」に下絵が残っています。
表に福禄壽、裏に鶴で、高蒔絵が見事です。緒締に珊瑚珠、根付に蒔絵の桃根付を取り合わせています。
アメリカの富豪で美術コレクターとして知られるヘンリー・オブボーンズ・ハヴマイヤー
と、ウイリアム.F.デュポンの旧蔵を経てきた名品です。
 意匠 : 意匠 :

 狩野晴川院養信がまだ部屋住みで絵師見習だったころに描いた「福禄壽に鶴図」の印籠下絵に基づいています。
この下絵は豊川家に代々伝えられた「印籠下画帖」に貼りこまれており、「玉川斎」の署名があります。
表の杖を持った福禄壽の傍らには蓑亀を配し、裏には二羽の鶴を配しています。下絵の写真は英文誌”DARUMA”16号(1997年)に掲載しています。実作に際して、下絵にはなかった吹雪を降らせ、「玉川斎」の下絵銘は書かれませんでした。
狩野晴川院養信がまだ部屋住みで絵師見習だったころに描いた「福禄壽に鶴図」の印籠下絵に基づいています。
この下絵は豊川家に代々伝えられた「印籠下画帖」に貼りこまれており、「玉川斎」の署名があります。
表の杖を持った福禄壽の傍らには蓑亀を配し、裏には二羽の鶴を配しています。下絵の写真は英文誌”DARUMA”16号(1997年)に掲載しています。実作に際して、下絵にはなかった吹雪を降らせ、「玉川斎」の下絵銘は書かれませんでした。
 狩野養信 : 狩野養信 :
 狩野養信は、木挽町狩野家の当主で幕府の絵師の総帥です。
初め玉川を号し、文化7年(1810)から父・伊川院栄信の見習を始めましたが、文化11年(1814)
に12代将軍・徳川家慶の世子・竹千代が没して玉樹院と謚されたため、「玉」の字を憚って「晴川」と改名し、後に法眼また法印に進みました。
江戸城障壁画の総指揮をとったことや、「公用日記」を遺したことで有名です。
狩野養信は、木挽町狩野家の当主で幕府の絵師の総帥です。
初め玉川を号し、文化7年(1810)から父・伊川院栄信の見習を始めましたが、文化11年(1814)
に12代将軍・徳川家慶の世子・竹千代が没して玉樹院と謚されたため、「玉」の字を憚って「晴川」と改名し、後に法眼また法印に進みました。
江戸城障壁画の総指揮をとったことや、「公用日記」を遺したことで有名です。
 形状 : 形状 :
江戸形、5段の格調高い形状です。天地は高く甲を盛っています。
2代楊溪の印籠に比べて素地が薄く軽く作られています。

 技法 : 技法 :
・金粉溜地に高蒔絵で福禄壽の肉取りが非常に見事です。0.6mmの高上げをしていますが、
もっと上がっているように見えます。高蒔絵の高上げには銀粉が使われています。
着衣の模様など非常に緻密です。青金粉や銀粉、朱漆も使われています。
そして福禄壽の目には玉眼が象嵌されています。裏の鶴も見事です。
羽根はうあいとなり、鶴の首の黒い部分には、
潤の漆で毛並みが描き込まれています。
尾羽は錫粉、銀粉そして先が黒漆と段階的に描かれています。赤銅粉蒔絵の爪は鋭さにも驚かされます。
 ・内部は金梨子地で、釦は金地です。
・内部は金梨子地で、釦は金地です。
 作銘 : 作銘 :
底部の左に「生泉斎」の蒔絵銘があります。
「生泉斎」銘は初代の豊川楊溪が稀に使用した別号と考えられます。
豊川家に伝えられた「印籠下画帳」には、「生泉斎」の銘が入った
秋草蒔絵の聞香炉の完成縮図も張り込まれています。
 伝来 : 伝来 :
 印籠の蓋裏に「HOH」のコレクション・シールがあり、
「336 SeiSenSAi Date 1700」とペン書きされています。
このシールは、アメリカの富豪で美術コレクターとして知られるヘンリー・オブボーンズ・ハヴマイヤー
のものです。
ハヴマイヤー夫妻はアメリカで最初に印象派のコレクションを築いたことで知られます。
そのコレクションは夫人によって大部分がアメリカ・メトロポリタン美術館等に遺贈され、
一部が売却されました。
印籠の蓋裏に「HOH」のコレクション・シールがあり、
「336 SeiSenSAi Date 1700」とペン書きされています。
このシールは、アメリカの富豪で美術コレクターとして知られるヘンリー・オブボーンズ・ハヴマイヤー
のものです。
ハヴマイヤー夫妻はアメリカで最初に印象派のコレクションを築いたことで知られます。
そのコレクションは夫人によって大部分がアメリカ・メトロポリタン美術館等に遺贈され、
一部が売却されました。
この印籠は、その後、ウイリアム.F.デュポン
の所蔵となり、約70年間誰の目にも触れず、1996年にクリスティーズ・ニューヨークに出品されました。
アメリカに渡ったのは19世紀末で、それ以前の伝来は分かりません。
しかし、下絵筆者と蒔絵師から考えて、おそらく徳川将軍家の所用品であったと考えられます。
 展観履歴 : 展観履歴 :
2019 東京富士美術館「サムライ・ダンディズム」展
↑先頭に戻る
作者について知る⇒
 豊川 楊溪(とよかわ ようけい)2代 1813〜1868
豊川 楊溪(とよかわ ようけい)2代 1813〜1868
五月蘆橘水鶏蒔絵印籠
(ごがつあしたちばなにくいなまきえいんろう)

 豊川楊渓(2代)作 豊川楊渓(2代)作
 法量 : 法量 :
縦86mm×横50mm×厚26mm
 製作年代 :江戸末期 製作年代 :江戸末期
嘉永〜文久頃(circa1850)
 鑑賞 : 鑑賞 :
豊川楊溪(2代)が徳川将軍家のために作った12本揃いの「定家詠花鳥十二ヶ月蒔絵揃印籠」のうちの1本です。
定家詠花鳥十二ヶ月の和歌に基づいたもので、江戸中期の刊本『絵本通宝志』に基づいて
印籠下絵が作られました。その印籠下絵は豊川家に代々伝えられた「印籠下画帳」に貼り込まれて現存しています。
金粉溜地に肉合研出蒔絵で水鶏を白蝶貝の彫嵌とした豪華な作品です。
ウイリアム.F.デュポンの旧蔵品で、長らくアメリアにありました。
珊瑚珠の緒締と葵蒔絵根付が取り合わされています。


 意匠 : 意匠 :
建保2年(1214)、後仁和寺宮が月次の花鳥の歌と絵の制作を企図し、
藤原定家(1162〜1241)が詠進した花と鳥に関する十二ヶ月の和歌(いわゆる定家詠花鳥十二ヶ月)の内、5月について詠んだ和歌に基づいています。
それぞれの月について、花と鳥をテーマに1首ずつ詠まれており、5月の和歌は
蘆橘 時鳥 なくや五月の 宿かほに かならずにほふ 軒のたち花
水鶏 槙の戸を たたく水鶏の 明ぼのに 人やあやめの 軒のうつりか
の2首です。
印籠の下絵の構図と添えられた和歌から、享保14年(1729)に刊行された、橘守國の挿絵による刊本『絵本通宝志』の挿絵に基づいていたことが分かっています。
そして実は橘守國もまた、別の刊本を基にしています。元禄4年(1691)に刊行された和歌の参考書『鴫の羽掻』の挿絵です。
橘守國の挿絵では、歌意により、水辺に菖蒲が咲き、水亭の屋根には菖蒲の葉が置かれ、
水亭の傍ら松と橘の木があり、橘の枝が水亭の軒から伸びています。
そして流水には2羽の水鶏が佇んでいます。
 豊川家に代々伝えられた「印籠下画帳」には、この印籠の下絵を含む12ヶ月分=12枚の印籠下絵が貼り込まれています(下絵の写真は英文誌”DARUMA”17号に掲載)。
幕府御用絵師が『絵本通宝志』の挿絵を基に印籠下絵に仕立てたようですが、下絵に落款はありません。
下絵は実作品に重ねると完全に一致するほど忠実に製作されましたが、
象嵌されている鳥はややデフォルメされてどれも大きめに作られました。
豊川家に代々伝えられた「印籠下画帳」には、この印籠の下絵を含む12ヶ月分=12枚の印籠下絵が貼り込まれています(下絵の写真は英文誌”DARUMA”17号に掲載)。
幕府御用絵師が『絵本通宝志』の挿絵を基に印籠下絵に仕立てたようですが、下絵に落款はありません。
下絵は実作品に重ねると完全に一致するほど忠実に製作されましたが、
象嵌されている鳥はややデフォルメされてどれも大きめに作られました。
印籠下絵では、『絵本通宝志』の挿絵を参考にしながら、
表裏の境目に松を配し、2羽の水鶏を水亭と反対の面に配した巧妙な構図になっています。
 形状 : 形状 :
江戸形4段、紐通付の印籠で、天地の甲を高く盛っています。

 技法 : 技法 :
・12か月すべての印籠が同寸法、同形状で、印籠下地は極めて高い精度で作られています。段の密閉度は高く、合口が見えないほどです。
・金粉溜地に肉合研出蒔絵で緻密に表しています。
そして珍しいのは、天地の金粉溜地を先に完全に仕上げてから両面の蒔絵に取り掛かっています。
その方がしっかり手で持てるので表裏の作業をしやすいのですが、天地の角に継ぎ目ができてしまうので、
普通の蒔絵師はしません。ところが2代楊溪は「山晴斎楊溪」在銘の「唐子蒔絵印籠」などでもこの手法を取っており、
しかも継ぎ目の痕跡がほとんど見えません。驚異的な技術です。
・源氏雲や土坡の部分には金切金を装飾的に規則正しく置いています。
・水鶏は白蝶貝を容彫して象嵌していますが、この部分は専門の芝山工に外注した可能性があります。
・段内部は金梨子地に平目粉を打ち込んだ豪奢な鹿子梨子地になっており、
合口と共に極めて高い精度で仕上げられています。
 作銘 : 作銘 :
豊川家の言い伝えによれば、十二ヶ月の揃い印籠は、徳川将軍家が正式な儀礼の際に用いるために制作を命じられ、
そのために銘を入れることが許されなかった、と云われていました。
豊川楊溪(2代)の活躍年代からみると、13代将軍・徳川家定と14代将軍・徳川家茂の可能性があり、
諸大名を謁する月次御礼の際に、その月の印籠を提げたのでしょう。
年代的には徳川家茂の方が可能性が高いと考えられます。
12本がまとめて作られたとみられますが、現存が確認されているのは、正月、5月、7月、8月、9月、10月、11月、12月の
8本で、いずれも無銘です。このうち正月と8月はその後行方不明になっています。
もし豊川楊溪の「印籠下画帳」が現存していなければ、これらが豊川楊溪の一連の作品であったことも、
十二ヶ月の揃い印籠であったことさえも分かりませんでした。
 伝来 : 伝来 :
ウイリアム.F.デュポンの旧蔵品で、1996年、クリスティーズ・ニューヨークのオークションに出品されました。
この時に出現したのは正月、5月、7月、8月、10月、11月、12月の7本です。
9月の印籠だけは、それより早く1990年のサザビース・ニューヨークに出品されており、
別の経路で伝来していたようです。
いずれも徳川将軍家の所用品と考えられ、明治の初めにアメリカに渡ったものと考えられます。
 展観履歴 : 展観履歴 :
2002 国立歴史民俗博物館・岡崎市立美術館「男も女も装身具」展
2019 東京富士美術館「サムライ・ダンディズム」展
2021 国立能楽堂資料展示室「日本人と自然 能楽と日本美術」
2023 MIHO MUSEUM「蒔絵百花繚乱」展
↑先頭に戻る
数珠払子蒔絵木刀
(じゅずにほっすまきえぼくとう)
 豊川楊溪(2代)作 石村近江木地 豊川楊溪(2代)作 石村近江木地
 法量 : 全長370mm 法量 : 全長370mm
 製作年代 : 江戸末期 天保〜安政頃(circa1850) 製作年代 : 江戸末期 天保〜安政頃(circa1850)
 鑑賞 : 鑑賞 :
三味線工・石村近江が作った木地に豊川楊溪(2代)が蒔絵した茶刀で、数珠に払子が高蒔絵で表されています。富裕な大名などの特注品とみられます。
柴田令哉(1850〜1915)の旧蔵品で、その遺著『漆器図録』にも掲載された名品です。


 意匠 : 意匠 :
数珠に払子の意匠で、実に卓越した構図です。仏門に入った大名の隠居などが依頼したものとみられます。

 形状 : 形状 :
腰反りが強く、木刀としては特異な形状です。鎬を立て、刃方に面を取り、棟を丸くしています。
栗形の代わりに、下緒を付ける象牙の留め具を付けています。
 技法 : 技法 :
 ・柞の素地を削った木刀で、頭部分と下緒を通す留め具には象牙を、鐺には鉄刀木が使われています。
裏面には木地を手掛けた石村近江の焼印があり、三味線に使用する材料を用いて製作した素地といえます。
・柞の素地を削った木刀で、頭部分と下緒を通す留め具には象牙を、鐺には鉄刀木が使われています。
裏面には木地を手掛けた石村近江の焼印があり、三味線に使用する材料を用いて製作した素地といえます。
 ・数珠に払子は高蒔絵で表しています。
払子のヤクの毛の白さは銀粉の付描で表し、元から先まで1本につながり、毛先の表現が特に見事です。
数珠の玉は黒で、親玉と向玉は四分一粉になっています。ボサ玉は金粉で、総は栗色でバラ筆で何度も描き載せて質感をよく表しています。
・数珠に払子は高蒔絵で表しています。
払子のヤクの毛の白さは銀粉の付描で表し、元から先まで1本につながり、毛先の表現が特に見事です。
数珠の玉は黒で、親玉と向玉は四分一粉になっています。ボサ玉は金粉で、総は栗色でバラ筆で何度も描き載せて質感をよく表しています。
 作銘 : 作銘 :

 指裏の鐺寄りに、三味線工・石村近江による「近江」の焼印があり、棟の鐺寄りに「楊溪(花押)」の蒔絵銘があります。
指裏の鐺寄りに、三味線工・石村近江による「近江」の焼印があり、棟の鐺寄りに「楊溪(花押)」の蒔絵銘があります。
 石村近江 : 石村近江 :
石村近江は2代目が京都から江戸に移り住んだ三味線工で、幕末の11代・石村近江(?〜1865)の作になるものと考えられます。
 伝来 : 伝来 :
明治の終わりごろ、柴田是真の長男・令哉は楊溪作のこの木刀と楊溪作の印籠を所蔵していました。
しかしこれほどの蒔絵の技術を持った「楊溪」が何者か分からず、どのような人物だったのか知りたかったようです。
そこで令哉は明治35年(1902)、日本漆工会の例会にこの木刀を持参して披露しました。
『日本漆工会雑誌』第14号には、「品定め」として記事があり、柴田令哉と赤塚自得(1871〜1936)とのやりとりが記されています。
「品定め」のコーナーは後にも先にもこの号のみです。
結局、出席していた会員も誰一人「楊溪」を知らず、広く情報を集めようとしたと考えられます。
「楊溪」は『東京名工鑑』にも掲載されていますが、「豊川彦八 業名山晴斎」の名でしか記載がなく、
「楊溪」という名を誰も知らなかったのでしょう。
実は『日本漆工会雑誌』の同じ号には日本漆工会の会員名簿が掲載されており、作者の子にあたる3代目の豊川楊溪も会員として掲載されていますが、
この記事に何ら反論をした形跡がありません。代々名利を求めなかったので名乗り出ることはなかったのでしょう。
赤塚自得によって、「玉溪」こと石井有得斎と関係があるのではないか、との発言がみられます(実際には無関係)。
そして玉総については、
赤塚自得は「技術は殊に数珠の玉総の揚げ方に於て一種の妙味を有す、其遣口は作者の一段苦心したるものにして、普通の総の書き方と大に異なり、糸の切口の重なりを「バラ筆」にて数回に書のせ、切口の意を表したる處一入よし」
と高く評価しています。
また柴田令哉が原寸展開図を書き起こして『日本漆工会雑誌』の附録とし、
柴田令哉没後に刊行された柴田令哉遺著『漆器図録』にも掲載されています。
2022年、約120年ぶりに発見しました。

 「漆器図録」 : 「漆器図録」 :
「漆器図録」は、日本漆工会の例会に出品された古漆器の名品を柴田是真の長男・令哉が
毎回展開図に描き起こして『日本漆工会雑誌』の附録としてたものです。令哉没後に再編集されて
柴田令哉遺著『漆器図録』として13巻組で刊行されました。

↑先頭に戻る
作者について知る⇒
|
2023年 5月28日UP
2024年 5月 5日更新
|
|