 白井 可交斎(しらい かこうさい) 生没年未詳 白井 可交斎(しらい かこうさい) 生没年未詳
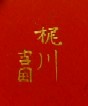
 流派: 梶川派 流派: 梶川派
 略歴: 略歴:
これまで可交斎については、
幕末の江戸の印籠蒔絵師で、通称が白井松五郎、可交斎枩山
と号したことぐらいしかわかっていませんでした。作風は梶川風で、印籠・根付・盃などが多く現存していました。
その後、ライデン国立民族学博物館に所蔵される下絵集の下絵類と
 梶川・可交斎・松花斎などの在銘作品とが合致するため、
梶川家の一門であろうとの推測は確実視されてきました。
梶川・可交斎・松花斎などの在銘作品とが合致するため、
梶川家の一門であろうとの推測は確実視されてきました。
さらに最近になって可交斎の作品に「枩山/吉国」・「可交斎/吉国」
という在銘のものを数点発見しました。その上、「梶川吉国」銘の作品も確認しました。
このことから、はじめは梶川一門の工人として「梶川吉国」と銘し(右上)、
後に名工として独立して、「可交斎枩山」(右下)や「枩山/吉国」・「可交斎/吉国」と銘したと推測するに至りました。
また彦根藩主井伊家に伝来した「不忍池蒔絵盃」(彦根城博物館蔵)が、
文化8年(1811)に城中で将軍家から拝領したものであることから、その活躍は文化から安政と推測され、
将軍家の御用を勤めていたことも確実になりました。
しかし正確な生没年や住所など、詳しいことは依然として何も判っていません。
 作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:
・根津美術館(寿老人蒔絵象嵌印籠)
・静嘉堂文庫美術館(風雪三顧蒔絵象嵌印籠・流水南天蒔絵印籠)
・東京富士美術館(足柄山蒔絵印籠
・桜紅葉蒔絵印籠
・象唐子蒔絵印籠
・円窓架鷹蒔絵印籠)
・茨城県立歴史館(◎千羽鶴蒔絵印籠)
・大阪市立美術館(富士芝浜蒔絵盃・蓬莱蒔絵三組盃・鯉富士龍蒔絵三組盃・水道橋蒔絵盃)
・彦根城博物館(不忍池蒔絵盃)
・立花家史料館(波鯉蒔絵盃
・六歌仙蒔絵盃・吉野山蒔絵盃・富士川蒔絵盃・吾妻橋蒔絵盃・隅田川蒔絵盃
)
・雷神門蒔絵盃・三囲社蒔絵盃)
作品を見る⇒
| 


